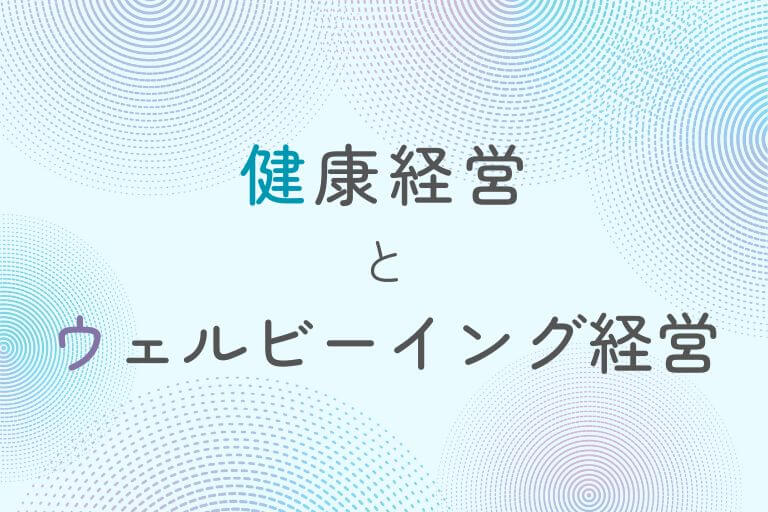ウェルビーイング経営が拓くSDGs達成への道筋
近年、企業の持続可能性を高める経営戦略として「ウェルビーイング経営」が注目されています。
従業員の心身の健康や働きがいを重視するこの考え方は、SDGs(持続可能な開発目標)とも深い関わりを持ち、企業の社会的責任を果たすうえで欠かせない要素です。
この記事では、ウェルビーイング経営の定義からSDGsとの関係、企業が実際に取り組むメリットと方法、そして国内外の具体的な事例までを網羅的に解説します。
「ウェルビーイング経営×SDGs」に本気で取り組みたい方にとって、実践のヒントとなる内容をわかりやすく整理していますので、是非参考にしてみてくださいね。
ウェルビーイング経営とは?SDGsとのつながりと基本理解

ウェルビーイング経営とは、従業員一人ひとりの心身の健康、社会的つながり、自己実現を重視した経営手法です。
単なる業績重視の方針から、「人を中心にした経営」へと移行する動きが国内でも加速しています。
この考え方は、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の中でも、特に「目標3:すべての人に健康と福祉を」や「目標8:働きがいも経済成長も」と深く関わっています。
企業によるウェルビーイング経営の実践は、社内施策にとどまらず、社会課題の解決にも寄与する取り組みといえるでしょう。
ウェルビーイングの定義と広がる概念
ウェルビーイング(Well-being)は、身体的・精神的・社会的に満たされた状態を意味し、1948年にWHOが定めた「健康」の定義にも含まれています。
かつては医療や福祉の分野で使われていた言葉ですが、今では教育、ビジネス、行政の場面でも重要なキーワードとして認識されるようになりました。
企業活動の中では、「ウェルビーイング経営」として従業員の幸福や健康を軸にした組織運営に取り組む事例が増えています。
PERMA・ギャラップ・幸福学の指標モデル
ウェルビーイングは抽象的に感じられるかもしれませんが、いくつかの理論に基づいて構成されており、数値や行動で把握することも可能です。
代表的なモデルを以下にまとめました。
| モデル | 内容 |
|---|---|
| PERMA(セリグマン) | Positive Emotion, Engagement, Relationships, Meaning, Achievementの5つの要素で構成される心理学モデル |
| ギャラップ社の5要素 | キャリア、ソーシャル、フィナンシャル、フィジカル、コミュニティの各側面からウェルビーイングを評価 |
| 前野隆司の4因子 | 「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」の4つの感情的要素で幸福感を説明 |
これらのフレームワークを活用することで、従業員の状態を可視化し、職場環境の改善や人事戦略に生かすことができます。
抽象的な“幸福”という概念も、こうしたモデルを取り入れることで施策として組み込みやすくなり、経営への実装が現実的になります。
SDGs目標3・8とウェルビーイングの関係

SDGsの中で、ウェルビーイング経営と特に関わりが深いのが「目標3:すべての人に健康と福祉を」と「目標8:働きがいも経済成長も」です。
- 目標3:すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)
- 目標8:働きがいも経済成長も(Decent Work and Economic Growth)
健康的な生活と安心して働ける環境は、個人の充実感を支えるだけでなく、社会全体の持続可能性にもつながります。
企業が従業員の健康や働きがいを向上させる取り組みは、そのままSDGsへの貢献として評価され、社外からの信頼や企業価値の向上にもつながっていきます。
注目される背景:多様化・人材課題・コロナ後の変化

ウェルビーイングが企業経営で注目される背景には、社会構造や働き方に関する変化がいくつも重なっています。
- 価値観の多様化:個人が「自分らしく働く」ことを重視するようになった
- 人材不足:少子高齢化により生産年齢人口が減少し、人材確保が経営課題に
- コロナ以降の変化:リモートワークの拡大やメンタルヘルスへの関心が急増
こうした変化に対応するためには、従来の働き方や人事制度を見直し、より柔軟で多様な価値観に応える経営が求められます。
その中心にあるのがウェルビーイングであり、人を重視する経営が企業の競争力を左右する時代が到来しています。
SDGs達成の鍵としてのウェルビーイング経営

SDGsは「持続可能な開発目標」の略で、2030年までに世界が取り組むべき課題を明確にした国際的な枠組みです。
内容には、貧困や気候変動といったグローバルな問題だけでなく、働き方や健康といった企業経営に直結する目標も含まれています。
中でもウェルビーイング経営は、「目標3:すべての人に健康と福祉を」や「目標8:働きがいも経済成長も」と強く結びついています。
さらに、企業の内外にポジティブな影響をもたらす点で、「目標5:ジェンダー平等」や「目標10:人や国の不平等をなくそう」などの領域にも関係します。
経営にSDGsの視点を組み込むうえで、ウェルビーイングは横断的な効果をもつ実践的な入り口といえるでしょう。
SDGsを経営に落とし込むとはどういうことか
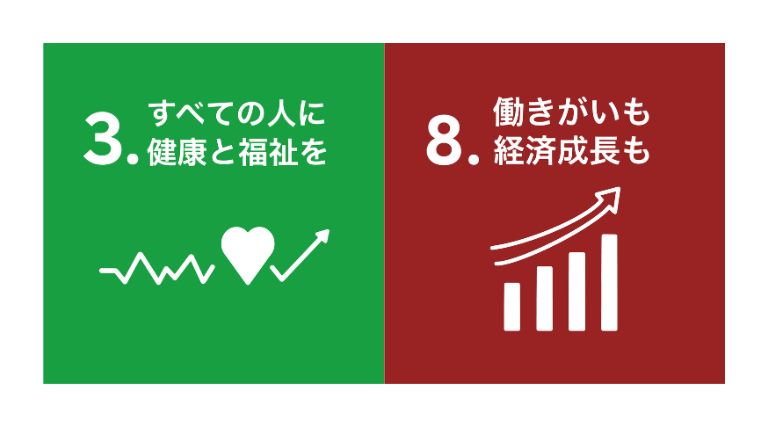
SDGsに取り組む企業は増えていますが、多くは自社の事業との接点が不明瞭なまま、「なんとなく良さそう」な取り組みに留まっているケースもあります。
ウェルビーイングは、従業員の状態や職場環境と直結するため、目標へのアプローチが具体化しやすい特徴があります。
例えば、福利厚生や健康支援の強化を通じて「目標3」への貢献を可視化でき、採用制度や職場文化の見直しは「目標8」との接点になります。
このように、日々の業務レベルにSDGsを落とし込む具体的な入口として、ウェルビーイングは非常に実効性の高い手段です。
定性的・定量的な評価基準を整えれば、取り組みの進捗も継続的に可視化できます。
健康経営との違いと相乗効果
先述した通り、健康経営とウェルビーイング経営はしばしば混同されがちですが、アプローチの広さに違いがあります。
健康経営はあくまで“体調”の管理が主眼ですが、ウェルビーイングは“人としての幸福”を起点にします。
たとえば「食事指導」や「運動支援」は健康経営に近い施策ですが、「キャリア自律支援」や「人間関係のサポート」はウェルビーイングの範囲です。
両者を組み合わせることで、「心身の健康+やりがい」という全体最適を実現できます。
結果的に離職率や労災リスクの低下といった、経営視点での成果にもつながります。
ESG・人的資本経営との接点
ESG経営の「S(Social)」領域では、従業員の権利や職場環境への配慮が評価対象になります。
人的資本経営の視点からも、個人の幸福感を重視するウェルビーイングは、企業の中長期的成長に直結する要素です。
以下は、ウェルビーイングが支援するESG・人的資本経営の代表的なポイントです。
| 領域 | ウェルビーイングによる具体的貢献 |
|---|---|
| ESGのS(社会) | ハラスメント対策、労働安全、ダイバーシティの推進 |
| 人的資本 | キャリア開発、従業員満足度、離職率の低減 |
加えて、国際的なサステナビリティ開示ルールでも、人的資本・ウェルビーイング関連の情報開示が求められる傾向にあります。
つまり、企業の信頼性や市場評価にも直接関係してくるのです。
企業ブランド・採用力・持続可能性への影響
ウェルビーイングの視点を持つ企業は、社外からの「共感」を得やすくなります。
求職者は、「この会社で自分らしく働けそうか」を見ています。
制度だけでなく、文化として浸透しているかも重要なチェックポイントです。
また、社内から見ても、自分が大切にされていると実感できる職場は、離職の抑止力になります。
次のような観点で、ウェルビーイング経営が企業の持続可能性を支えています。
- ブランディング:企業価値やイメージの向上
- 人材獲得:優秀な人材が集まりやすくなる
- 定着率向上:従業員エンゲージメントが高まる
結果として、短期的なコストではなく、長期的な投資と捉えるべき戦略になります。
単なるPRでは終わらせず、実態として信頼される組織を築くことが、次代の経営に不可欠です。
企業が取り組むウェルビーイング経営の実践ポイント

ウェルビーイング経営は理念だけでなく、実際の行動と仕組みに落とし込まれてこそ意味を持ちます。
ここでは、企業が具体的に取り組むべき5つのポイントを紹介します。
労働環境の整備と柔軟な働き方
長時間労働の是正や勤務形態の柔軟化は、働きやすい環境づくりの基本です。
テレワークやフレックス制度を導入し、個々の生活状況に合わせた選択肢を用意することで、従業員の満足度を高められます。
また、育児・介護といったライフステージに応じたサポートも不可欠です。
こうした配慮の積み重ねが、安心して働き続けられる職場づくりにつながります。
健康支援とメンタルヘルスケア体制の構築
従業員の健康維持には、定期的な健診だけでなく、早期対応を可能にするサポート体制の整備が求められます。
産業医との連携やストレスチェック、メンタルケア研修の実施が重要な基盤になります。
気軽に相談できる窓口の設置や、オープンに話せる風土づくりも大切です。
体調や気分の変化に気づきやすい職場環境こそ、継続的なパフォーマンスを支える要因となります。
心理的安全性と社内コミュニケーションの強化
安心して意見が言える環境づくりは、組織の信頼関係を深める鍵です。
1on1ミーティングやチーム対話の場を意図的に設けることで、心理的安全性を醸成できます。
特にリモートワークが広がる今、コミュニケーションの質を意識的に設計する必要があります。
福利厚生の再設計とライフスタイル支援
従業員の生活に寄り添った福利厚生は、エンゲージメントの向上につながります。
レジャーや運動支援、子育てとの両立支援など、選択できる制度の整備が有効です。
一人ひとりのライフスタイルに合ったサポートが、多様性を受け入れる土台になります。
押し付けにならない設計と測定の仕組み化
ウェルビーイング施策は、従業員の「主体性」を引き出すものであるべきです。
多様なニーズに応える選択肢型の設計と、数値だけに頼らない柔軟な測定が求められます。
定量・定性の両面から声を拾い、アップデートを前提に運用する姿勢がカギとなります。
従業員ごとの状況や価値観を尊重し、本人の納得感を伴う取り組みとすることが重要です。
画一的な制度では見えづらい「気づき」や「違和感」に、早期から対応できる柔軟性も求められます。
記事のまとめ

ウェルビーイング経営は、一過性のトレンドではありません。
従業員の健康や幸福を土台に、企業が社会と共に成長するための本質的なアプローチです。
SDGsの中でも、目標3「健康と福祉」や目標8「働きがいと経済成長」と強く結びつき、ESGや人的資本経営とも接続します。
とはいえ、ウェルビーイングの実現は理念だけでは成り立ちません。
労働環境、柔軟な制度設計、心理的安全性、ライフスタイル支援、そして押し付けにならない仕組み——すべてが揃ってはじめて、企業文化として根づきます。
自社にとっての「働きやすさ」や「幸福」とは何かを問い直すことが、SDGs達成の第一歩になります。
今、何を優先すべきか。誰のために、どんな未来を目指すのか。
ウェルビーイング経営は、その問いへの具体的な答えになり得ます。
ぜひこの機会に、自社の経営に「人を中心に据える」という視点を加えてみてください。
- ・本コンテンツの情報は、充分に注意を払い信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- ・本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。医療上のアドバイスや診断、治療に関しては、必ず医療従事者にご相談ください。
- ・本コンテンツの情報は、その情報またはリンク先の情報の正確性、有効性、安全性、合目的性等を補償したものではありません。
- ・本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
- ・本コンテンツで紹介しているSUGUME検査キットは、研究用であり体外診断用医薬品ではございません。