
ウェルビーイング経営の実践ステップ!企業価値を高める効果的な取り組みとは
従業員の定着率、生産性、エンゲージメント——。
これらを本気で高めたい企業が今、注目しているのが、社員の健康と幸福に焦点を当てた「ウェルビーイング経営」です。
「取り組みたいけど、何から始めればいいのかわからない」「やってはいるけど効果が実感できない」という声も多いなか、この記事では、実践企業に共通する“取り組みのステップ”を整理しながら、具体例や注意点も交えてわかりやすく解説します。
これから始めたい企業も、すでに導入済みの企業も、自社に合ったウェルビーイング経営のヒントを見つけていただけるはずです。
ウェルビーイング経営の基本と背景

働き方の多様化、SDGsの浸透、そして人的資本経営への注目が高まるなか、従業員の幸福度に着目した「ウェルビーイング経営」への取り組みが企業の新たな成長戦略として注目されています。
単なる健康施策ではなく、個々の働きがい・社会的つながり・心理的安全性といった要素を土台に、組織全体の生産性向上も視野に入れた、従業員も企業も持続的に成長できる環境づくりを目指す考え方です。
ウェルビーイング経営とは
ウェルビーイング経営とは、従業員が「身体的・精神的・社会的」に満たされた状態で働けるように組織全体で取り組む経営手法です。
働きがいや人間関係、柔軟な働き方など、従業員の主観的な幸福感(=主観的ウェルビーイング)を中心に据えた組織運営が特徴です。
なぜ多くの企業が取り組みはじめたのか
背景には、採用難・離職率の高さ・エンゲージメント低下といった人材課題があります。
さらに、以下のような社会的要請が後押ししています。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 働き方改革 | 長時間労働の是正やテレワーク導入で、従業員の満足度向上が重要に |
| SDGsの普及 | 「すべての人に健康と福祉を」など、企業の社会的責任が拡大 |
| 人的資本経営 | 従業員への投資が企業価値に直結する時代へ |
こうした流れのなかで、「人を大切にする企業」に注目が集まり、結果的に採用力・定着率・生産性を高めるウェルビーイング経営が支持されています。
大企業だけでなく、中小企業でも人的資本経営の観点から導入が進んでいます。
ウェルビーイング経営の取り組み3ステップ

ウェルビーイング経営は「施策を導入して終わり」ではなく、継続的に改善を重ねていくプロセス型のアプローチです。
うまく進めている企業は、一気にすべてを変えるのではなく、現状の課題を見極めながら優先順位をつけて少しずつウェルビーイング経営を前進させています。
ここでは、多くの企業で採用されている「把握・実行・改善」の3ステップで考えていきます。
ステップ1:現状把握と課題の可視化
最初のステップでは、自社のウェルビーイングの現在地を把握し、どこにボトルネックがあるのかを整理します。
「何が問題か分からない」状態では、施策もピントがずれます。
定性的・定量的な視点をバランスよく使って可視化することがポイントです。
- 従業員サーベイ(ES:満足度、EX:体験の質)を定期実施
- 1on1で拾えた現場の「声」を定量化・分類
- 組織状態(エンゲージメント、離職率、有休取得率)の棚卸し
外部ベンチマークとの比較も、現実を冷静に捉えるヒントになります。
定期的なサーベイで社員の声を幸福度指標として活用している企業も増えています。
ステップ2:施策の企画と実行
課題が明らかになったら、いよいよ実行フェーズです。
ここで重要なのは、「バラバラな施策」ではなく、全体像の中に位置づけた一貫性ある取り組みにすることです。
- 課題別に目的を明確化(例:メンタル不調 → 相談窓口整備)
- 小さく始めて反応を見ながら、施策を精度化
- 現場の巻き込みと経営陣のメッセージ発信を両立
「誰のための施策か」が曖昧だと、形骸化しやすくなるため、ユーザー視点で設計しましょう。
具体的なKPIを設定し、管理職を含めた組織全体で取り組むことが重要です。
ステップ3:データで検証し改善する
施策は実行して終わりではなく、きちんと効果検証し、必要に応じて改善することが欠かせません。
そのためには、KPIの設定と測定方法の明確化が前提になります。
- 実施前後で従業員サーベイを比較(信頼スコア、帰属意識など)
- 施策参加率、利用率、社内の口コミなど行動データの分析
- 部署・階層別(管理職と一般社員など)の温度差に注目し、対応を分ける
数字と現場の声の両面で振り返ることが、より本質的な改善につながります。
【施策カテゴリ別】具体的な取り組み例

ウェルビーイング経営の成功には、課題の種類に応じた具体的な施策の選定が欠かせません。
ここでは、現場で特に導入事例が多い6つの施策カテゴリを紹介します。
- 労働環境の改善(フレックス・テレワーク等)
- メンタルヘルス・産業医との連携
- コミュニケーション活性化の仕組み
- 従業員サーベイ(EX・ES)の活用
- 福利厚生の整備と平等な運用
- DX推進(ワークフローシステムなど)
すべてに着手する必要はありません。
優先度やリソースに応じて、自社にフィットするものから取り組み始めるのが現実的です。
労働環境の改善(フレックス・テレワーク等)
勤務場所や時間に柔軟性を持たせることで、従業員の裁量や生活リズムに合った働き方を支援します。
とくに育児や介護との両立が必要な人材にとっては、離職防止や定着率・エンゲージメントに直結する要素です。
- フレックスタイム制度、時差出勤制度の導入
- 週〇回の在宅勤務OKなど、ハイブリッドワークの導入
- 副業・兼業の解禁や短時間正社員制度の整備
メンタルヘルス・産業医との連携
心と身体の健康を守る体制づくりは、社会的責任であるとともに、業績や雇用リスクを左右する重要課題です。
「相談しやすさ」や「気づきの早さ」をどう仕組み化するかがポイントになります。
- 年1回のストレスチェック+フォロー面談
- 常勤の産業医や外部カウンセラーとの連携強化
- セルフケアを促すeラーニングや朝礼テーマの導入
コミュニケーション活性化の仕組み
日常の人間関係がギスギスしていては、施策も浸透しません。
「雑談しやすい」「相談しやすい」風土をつくることが、組織の心理的安全性の第一歩です。
KPIで測定しづらい部分ですが、重要な取り組みです。
- 1on1ミーティングの定着と、上司向けコーチング研修
- 部署を横断したプロジェクト活動・ランチ交流
- Slackや社内SNSで「ありがとう」を伝える文化づくり
従業員サーベイ(EX・ES)の活用
「サーベイデータとEX(従業員体験)の分析は、ウェルビーイング経営の土台となります。
「何が課題か」「どう感じているか」は主観情報。
だからこそ、定量的なサーベイで可視化する仕組みが必要です。
実施して終わりではなく、「結果から何を読み解くか」が問われます。
- 半年~年1回のES(従業員満足度)調査
- オンボーディングや離職面談などEX調査の設計
- スコアの推移を見て、組織改善のヒントに
福利厚生の整備と平等な運用
福利厚生は「使われてこそ価値がある」もの。
提供して終わりではなく、利用率と満足度のモニタリングが重要です。
また、部署や属性で利用格差が出ないよう、設計段階からの配慮が求められます。
- 選べるカフェテリアプランやポイント型制度
- 医療費補助・スポーツ施設の割引・カウンセリング支援
- 利用実績の集計→改善サイクルへ活用
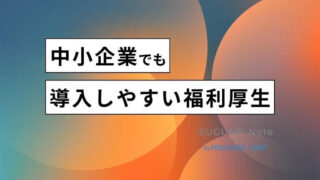
DX推進(ワークフローシステムなど)
アナログな業務プロセスは、属人化・非効率・ストレスの温床です。
DXへの取り組みは単なる効率化ではなく、従業員体験(EX)改善の起点にもなり得ます。
- 各種申請・稟議を電子化するワークフローシステム導入
- SlackやTeamsと連携して通知・承認を簡素化
- 申請フローの改善で「ムダな仕事」を見直す機会に
導入の注意点・デメリット

ウェルビーイング経営は注目される一方で、進め方を間違えると「施策だけが増え、成果につながらない」状態に陥ることもあります。
ここでは、よくある落とし穴や中小企業での進め方の工夫を整理します。
短期成果を求めすぎない
ウェルビーイング経営は、体制づくりや価値観の共有といった「文化変革」を伴う取り組みです。
従業員満足度やエンゲージメントが改善するまでには一定の時間がかかります。
短期的なKPIだけで評価すると、継続が困難になりやすいため注意が必要です。
健康や幸福など、数値化しにくい要素も大切にしましょう。
従業員とのギャップに注意
経営層が「良かれ」と思って導入した取り組みや施策が、現場には響かない。
こうしたミスマッチは、現場との信頼関係を損なう要因にもなります。
定量的なサーベイと、現場ヒアリングの両輪で「本音」を把握しておきましょう。
中小企業でも実践できるスモールスタートで徐々に拡大
資金や人員リソースが限られる中小企業でも、段階的に進めることは可能です。
たとえば、「まずはストレスチェックと1on1面談を導入」など、コストのかからない施策から始めて、効果が見えたら横展開するのが現実的です。
下記はスモールスタートで取りやすい施策例です。
- 勤怠データの分析 → 長時間労働の可視化
- 産業医と連携し、メンタル不調者の初期対応
- 感謝を伝え合う取り組みの社内キャンペーン
助成金や外部支援の活用も検討しよう
厚生労働省の「職場環境改善助成金」や、各自治体のウェルビーイング推進事業など、公的支援も増えてきました。
また、専門家のアドバイスを受けることで、社内だけでは気づけない設計の甘さや改善点が明確になることもあります。
予算の制約がある企業こそ、外部資源をうまく使って推進力を高めていきましょう。
ウェルビーイング経営の成功事例6選

ここからは、実際にウェルビーイング経営を取り入れて成果を上げている企業の取り組みを見ていきます。
業種や規模は異なっていても、「従業員の幸せと企業の成長を両立する」という共通の視点から、ユニークで実践的な工夫が行われています。
取り組み方に正解はありませんが、具体的な事例に触れることで、自社に合ったアイデアやヒントが見つかるはずです。
トヨタ:幸せの量産をミッションに
トヨタ自動車は「幸せの量産」をミッションに掲げ、モビリティ社会の発展と従業員の幸福を両立するウェルビーイング経営に取り組んでいます。
その取り組みの一環として、2021年より「Emotional Well-Being研究会」を立ち上げました。
国内外の製造現場に焦点を当て、「仕事を愛するとは何か?」「面倒見とは何か?」といった本質的なテーマを議論する場を設けています。
従業員一人ひとりの価値観や文化的背景に配慮し、全社一律の制度ではなく、現場ごとの課題に合わせた取り組みを模索している点が特徴です。
研究会では「認める」「面倒見」といったキーワードを軸に、世代間や職位間のギャップの解消に注力。
「三性の理」といった哲学的視点を導入しながら、組織内の関係性を再構築するアプローチを取っています。
今後は研究会で生まれたアイデアを複数の工場で実践し、それぞれの現場に適したウェルビーイングな職場づくりを進めていく予定です。
参考:幸せの量産をミッションに掲げる私たち従業員のWell-beingを見つめる | 未来につながる研究 | モビリティ | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト
積水ハウス:全従業員の「幸せ度」を見える化する取り組み
積水ハウスは「世界一幸せな会社」を目指し、従業員のウェルビーイングを重視した経営に取り組んでいます。
2020年からは、幸福経営学の第一人者・前野隆司教授の監修のもと、グループ約27,000人を対象に「幸せ度調査」を実施。
仕事のやりがいや自己成長、職場の人間関係などを多面的に測定し、結果は4年連続で一般平均を上回る水準を記録しています。
調査後は、結果を活用した職場単位の対話やワークショップを実施し、心理的安全性の高い職場づくりを推進。
一人ひとりが主体的に「幸せ」について考える文化を根づかせ、組織全体でウェルビーイングを高める仕組みへとつなげています。
参考:従業員の幸せ度調査 | 多様な働き方の推進 | ダイバーシティ&インクルージョン | 積水ハウス
楽天:CWO設置と全社横断で進めるウェルビーイング経営の取り組み
楽天は、「イノベーションを通じて人々と社会をエンパワーメントする」という企業ミッションのもと、ウェルビーイング経営に本格的に取り組んでいます。
2021年には、チーフウェルビーイングオフィサー(CWO)を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設立し、経営陣が横断的に関与する体制を構築。
ESG課題に対する意思決定や戦略立案を、経営レベルで進める仕組みを整えました。
従業員の心身の健康や心理的安全性を支える制度も拡充し、エンゲージメントやウェルビーイング指標の可視化を通じて、改善と成長を図る仕組みが動いています。
さらに、全社朝会や年次研修、社内コミュニティを通じて、従業員一人ひとりの意識を高める環境づくりにも注力。
自発的なサステナビリティ行動を表彰する「Sustainability Action Award」も導入し、ウェルビーイング経営を社内文化として根づかせています。
丸井グループ:社員主導で推進するウェルネス経営の取り組み
丸井グループでは「活力×基盤のウェルネス経営」を掲げ、従業員の健康と主体性を両立させる取り組みを推進しています。
特に特徴的なのが、手挙げ式で集まった社員が企画・実行を担うグループ横断プロジェクトです。
プロジェクトでは、職場ごとのアイデアでウォーキング企画や食習慣改善などの施策が生まれ、7割近くの社員が参加するまでに広がっています。
さらに管理職を対象に、レジリエンスを高める年間プログラムも実施。
組織全体の活力向上に向けて、従業員主導で継続的な取り組みが行われています。
参考:「手挙げ式」のグループ横断プロジェクトで、社員が自ら活力向上に取り組む|日本の人事部 健康経営
アシックス:創業理念を現場で体現する仕組みを推進
アシックスは、創業理念「健全な身体に健全な精神があれかし(Sound Mind, Sound Body)」を従業員自身が実感できる環境づくりを目指しています。
2023年度は「ヘルスリテラシーの向上と定着」をテーマに、以下の5つの施策を実施しました。
- 健康管理・増進体制の拡充
- ヘルスリテラシー(判断力・伝達力など)の支援
- 生活習慣改善に向けた支援
- メンタルヘルス対応の強化
- 多様な人材が活躍できる職場環境の整備
これらの取り組みは、健康行動の定着を促進し、社員のパフォーマンス向上にもつながっています。
たとえば、「80%以上の力を発揮できている」と回答した社員の割合は、2022年度の43.1%から2023年度は44.6%に改善しました。
アシックスは今後も、従業員とその家族を含めた持続的な健康促進を通じて、理念の実現に取り組んでいく方針です。
参考:「ASICS Well-being Report 2024(ASICS健康白書)」を公開|アシックス
味の素:自然と健康になれる職場環境を目指して
味の素グループは「働いているだけで自然と健康になれる会社」を掲げ、身体・精神・経済の3側面からWell-being向上を支援しています。
具体的には、セルフケアを軸にした健康維持の支援、資産形成教育、家族を含めたサポートなど、多角的な取り組みを展開。
健康寿命延伸を企業のパーパスに掲げ、社内外のパートナーと連携しながら、社員のイキイキとした働き方を支える環境づくりを進めています。
参考:健康経営 | Well-beingについての取り組み | 味の素株式会社
記事のまとめ:まずは自社に合った取り組みを見つけるところから

ウェルビーイング経営は「正解のない経営」です。
だからこそ、大切なのは他社をそのまま真似るのではなく、「自社に合った進め方」を見つけること。
まずは、現状把握→小さな施策の実行→振り返りという基本のステップを丁寧に回し、自社らしい取り組みを少しずつ積み上げていくのが現実的なアプローチでしょう。
健康と幸福のバランス、社員と組織の調和、そして生産性と離職率の改善を複合的に捉えることが大切です。
この記事が、自社なりのウェルビーイング経営をスタートするきっかけになれば幸いです。
- ・本コンテンツの情報は、充分に注意を払い信頼性の高い情報源から取得したものですが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- ・本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。医療上のアドバイスや診断、治療に関しては、必ず医療従事者にご相談ください。
- ・本コンテンツの情報は、その情報またはリンク先の情報の正確性、有効性、安全性、合目的性等を補償したものではありません。
- ・本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。
- ・本コンテンツで紹介しているSUGUME検査キットは、研究用であり体外診断用医薬品ではございません。







